if命令
今までのプログラムは上から下へ全ての行を実行していました。しかし、プログラムが本当に便利なのは条件によって、特定の処理をしたり、あるいはその処理をしなかったりということが可能だからです。これを「条件分岐」といいます。
「条件分岐」は信号機を思い浮かべるとわかりやすいでしょう。信号が青なら進み、赤なら止まります。プログラムでも同じように何かの条件を満たしていたら処理をして、満たしていなければしない、ということを指示することが出来るわけです。
「条件分岐」は、if文によって実現します。
☆if文の書き方1
if (条件式) {
条件式が正しいときの命令
・
・
}
ifの後に条件式を書いて、その条件式が正しいときだけ実行する命令を書くことが出来ます。条件式が正しいときに実行する命令は何行でも書けます。
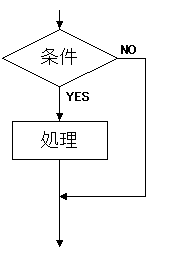
例えば以下のように使います。
str = prompt("値を入力してください","");
num = parseInt(str);
if( num == 10 ) {
alert( "あたり!" );
}
このプログラムではまずキーボードから値を入力し、それを数値データにして変数numに代入します。そして、if文で num == 10 という条件式を括弧の中に書いています。これはnumが10と等しいかどうかを調べているわけです。=を2つ書いていることに注意してください。 numが10であればこの条件式は正しいということになり、画面に「あたり!」と表示します。numが10でなければ何もしません。
if文の中身の部分は { から } までの間に書きます。この間の改行はあってもなくてもかまいません。if文の中身の部分については右に少しずらして書いていることに注意してください。これを段付け(インデント)といいます。これは空白では無くTABキーを押して段付けを行います。
段付けをしてもしなくても、プログラムは同じように動きますが、どこからどこまでがif文の中身なのかがわかりやすいように、通常は段付けを行います。
段付けはわかりやすく見やすいプログラムを書くためには必須の技術ですので、必ず段付けを行って書くような癖をつけてください。
このようにif文を使うことでさまざまな処理の分岐が可能になります。
問題6-1
キーボードから入力した文字列が"abc"だったら「あたり」と表示しよう
 プログラミング最初の一歩 JavaScript
プログラミング最初の一歩 JavaScript